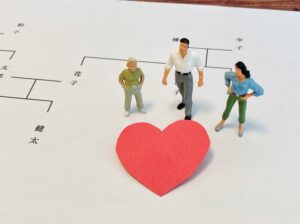高齢者の意思能力の有無は、法律行為の効力を左右する重要な問題です。
意思能力を有しないと無効になる
民法には、次のような規定があります。
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第3条の2となっているのは、民法の改正で追加された条文だからです。これまで意思能力がない者の法律行為が無効であることは、解釈上そうなっていましたが、法律上明文化されました。
意思能力とは何か
「意思能力」というのは、法律行為をするために有効に意思表示をする能力のことをいいますが、明確な定義があるわけではありません。そこで、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況」との関係が問題になります。
「弁識」とは、なじみのない日本語なので、便宜的に「理解する」とか「判断する」とかに言い換えてもよいかも知れません。
ややこしいですが「意思能力」と「判断能力」は区別されます。後述しますが、意思能力はあるが、判断能力が十分でないということがあり得るのです。
認知症のリスク
高齢者の意思能力が顕著な問題となるのは、認知症です。
認知症といっても、意思能力の有無については幅があるので、個々の行為に関する「判断能力」の有無は、それぞれ個別に判断すべきとされています。つまり、認知症によって、判断能力は不十分と診断されたが、意思能力はがあるので契約の締結はできるという常況が想定されることになります。
法律行為を行う上で、認知症の程度によって、契約等の必要な意思能力を有しないと解される可能性はあることは、極めて重要な問題です。
「法律行為ができない」ということは、例えば、①不動産などの自分の財産の管理や処分ができない、②遺産分割協議の結果が有効とみなされないということです。
また、③定期預金の解約などもできなくなります。
さらに「無効」と判断されてしまうと、それまでに行った法律行為は、第三者が介在していても、全部元に戻される可能性があります。
後見制度の利用
一方、法律行為をするのに十分な判断能力がないとみなされた場合、民法第7条の後見制度を利用することが考えられます。これは、判断能力の不十分な方々を、悪徳商法などの不利益な契約から保護・支援するための制度とされています。
先の例でいえば、判断能力が十分でない方は、後見制度の対象ですが、契約の締結ができる場合があるということになります。
なお、事理を弁識する能力の程度に応じて、法定後見には、補助・保佐・成年後見の類型があり、家庭裁判所への申立ての結果、家庭裁判所から選任された補助人・保佐人・成年後見人が付くことになります。
成年後見人の権利
さて、成年後見制度の対象となった人は、成年被後見人と呼ばれますが、では、この成年被後見人の方々は、以下の権利を有しているのでしょうか。
① 選挙権・被選挙権を行使すること
② 国家公務員になること
③ 地方公務員になること
④ 医師になること
⑤ 弁護士になること
⑥ 司法書士になること
⑦ 公認会計士になること
⑧ 税理士になること
⑨ 会社などの役員になること
ノーマライゼーションという考え
いずれも成年被後見人というだけでは、当然には欠格事由とはなりません(②~⑧については、個別審査をするということはあるようですが)。自分の財産の管理をするだけの判断能力がないとされている人が、医者として患者をみたり、取締役として経営判断ができるというのは、なかなか理解が難しいところではないかと思いますが、成年被後見人の方々の社会参加を促す必要があるという観点(ノーマライゼーション)からは、従来あった欠格条項を撤廃するという判断になったようです。
このように、認知症になったからといって、当然に法律行為ができなくなるとか、権利が当然に奪われるわけではありません。
実務上の問題
一方で、我々が仕事をする上で、この曖昧さはどうでしょうか。司法書士にとって、本人確認と意思確認はたいへん重要な責務です。せっかく仕事をしたのに、意思能力がなかったので無効です、さらに司法書士の責務を怠ったと言われたら、たまりません。
アルツハイマー患者の不動産売却に関して、東京高裁(H27.4.28)の判決ですが、このような記載があります。
「司法書士は、登記等の専門家として、依頼者の属性や依頼時の状況、依頼内容等の具体的な事情に照らし、登記申請意思の真実性に疑念を抱かせるに足りる客観的な状況がある場合には、これらの点について調査を尽くし、上記疑念を解消できない場合には、依頼業務の遂行を差し控えるべき注意義務を負っているものと解するのが相当である。」
上記の事例は注意義務を怠ったと言われてもおかしくない特殊なケース(司法書士に不法行為責任があるとされました。)であると切り捨てることもできるかもしれません。しかしながら、当事者の「登記申請意思」については、しっかりと確認をしておかないとたいへんなことになりかねません。
結果として、「登記申請意思」に疑義がある状態での業務遂行については、慎重にならざるを得ません。